欧州合同原子核研究機関(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LargeHadron Couider:LHC)では、周長27kmのトンネルの中を時計まわりと反時計まわりに陽子ビームが周り途中4か所でそれらを衝突させることが可能な構造になっています。この時に生み出されるエネルギーは、これまでの加速器で得られる最高エネルギーの約7倍を達成することが可能です。1994年12月以来14年の年月をかけて2008年9月に完成しましたが、約1週間後にヘリウムの大量流出事故が起き、その修理・改善のためには1年近い時間を要しました。建設費は約5000億円で、欧州の20か国に加えて、日本、アメリカ、インド、カナダ、ロシア等が貢献する国際プロジェクトです。日本は、加速器建設に総額138億5千万円を拠出し、技術的な貢献では、周回しているビームを衝突点で収束させ、高い輝度での衝突を可能にするための装置であるビーム収束用超伝導四極磁石の開発建設を行いました。
20世紀後半には「標準理論」という理論が確立し、物質の最小単位である素粒子やそれらの間に働く力がよく理解できるようになりました。この理論の中で鍵となるものがヒッグス機構というものです。標準理論が正しいとするならば、この理論から予言される電荷を持たない粒子(ヒッグス粒子)が存在するはずですが、未だ発見されていません。LHCでの実験の一番大きな目的は、このヒッグス粒子を発見して標準理論を最終的に確立することにあります。私たちの宇宙は縦横高さの空間3次元に時間の1次元を加えた4次元時空ですが、統一理論では、空間が3次元より次元数が多い可能性も指摘されていて、そのことによる影響がLHCで探るエネルギー領域に見えてくる可能性が指摘されています。さらに、それほどの高エネルギーを生み出すことが可能であれば、生成して瞬時に崩壊するレベルではあるものの、ブラックホールが生成されるかもしれません。
LHCでは、1秒間に陽子ビームが4千万回交差し、設計値の輝度(ルミノシティー)ではそのたびに平均約20個の陽子と陽子が衝突します。多くの場合は、それぞれの陽子の中にたくさんあるクォークやグルーオンが衝突して、たくさんの粒子を発生させます。それに対し、例えば予想されるヒッグス粒子は約1分間に一つ程度しかできません。ヒッグス粒子を探索するのは世界中の人たちの中から特定の一人を探し出すより難しい作業になる計算です。このため、衝突を見逃さないように、観測装置で衝突点の周りをできるだけ全方向から覆ったうえで、発生粒子の特徴(粒子の種別、エネルギーの大きさ、方向)を精度よく測る検出器が必要となります。このような理由で、種類の異なった検出器を何層にも重ねた巨大な測定器が必要となります。
LHCでは、主に四つの大きな国際共同実験(ATLAS、CMS、ALICE、LHCb)が組織されました。そのうちのATLAS(アトラス)とCMSが、未発見のヒッグス粒子の発見を目指した汎用実験グループである。日本からは約100人が、全体では37の国と地域からの約3000人が参加している。アトラス測定器は直径25m長さ44m、内部から外に向って順に、磁場中の粒子の飛跡を見て運動量を測る内部飛跡検出器、粒子を止めてエネルギーを測るカロリメータ、そこを突き抜けてくるミューオンを検出する測定器が衝突点を覆っている。アトラス測定器全体で約9000万個の検出器が積み重なっている。
今後のLHCの運用は、本来の性能の約半分の出力で2011年の終わりまでほぼ休みなく運転する計画です。現状でどこまでエネルギーを上げられるかについては、今回の連続運転レベルの3.5TeVビームの運転は安全であると結論付けられています。けれど、装置全体に設計・建設上の不備が見つかっているため、さらに出力を上げて、ビームあたり7TeVの運転をする前には、全ての接続部の改善をしなくてはならないことがわかっています。全ての接続部を直すには10か月はかかると見積もられています。現時点の計画では、3.5TeVビームで2011年まで実験を行い、その後で1年近いシャットダウンをして改修を行った後に7TeVビーム運転へ進むことになっています。3.5TeVビームで運転することで、接続部の改善の準備の間に加速器が他の問題がなく、長期に安定して動くことを確認するとともに、実験グループにも十分なデータを供給できる見通しです。
No.(2730) |
|
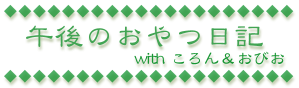
 ・・・ハッピーころん
・・・ハッピーころん ・・・ハッピーでないころん
・・・ハッピーでないころん ・・・ハッピーおびお
・・・ハッピーおびお ・・・ハッピーでないおびお
・・・ハッピーでないおびお ・・・ころんのつれづれ
・・・ころんのつれづれ